はじめに
はじめまして。この4月から株式会社TKLab.Ambitionの一員としてお世話になります、渡邉佳和子(わたなべかなこ)と申します。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。獣医師になって丸3年、牛の臨床に携わって述べ丸2年。まだまだひよっこながらも、日々牛たちとじっと見つめあうことで改めて気付かせてもらった、「これは私自身が生きていくうえでも大事だなあ」と感じたことを、今回は2点に分けて書き留めておきたいと思います。
と言いましても、よく見かけるような「命の大切さ」「命をいただくということ」といった内容はもう様々な場所で目にされてきたことでしょう。わたしが共有したいのは、もっと身近で簡単な内容です。なーんだそんなこと!と笑われてしまうかもしれませんが、小娘の独り言にしばしお付き合いください。
食べることは、生きること

物言わぬ牛たちの体調不良を感じ取るための最も重要なサインのひとつが、「食べる量」です。”ここ数日あまり食べていない” “今朝から急に食べなくなった” 酪農家さんからそんな稟告をいただくと、私は牛の前でぐっと集中力を高め、その原因がどこにあるのかをじっくり見極めます。治療を経て「食べる量」がもとに戻ることは、牛が元気になったしるしであり、私はほっと一安心。それほど「食べること」は牛の体調によって大きく左右されてしまう営みなのです。

ところが、その体調を悪くする原因もまた「食べること」であることが多々あります。一部が腐ったりかびてしまったエサを食べたことで下痢をした、なんてことは珍しくありません。
このように「エサそのもの」に問題がある場合、ほとんどの場合は原因の除去が解決につながります。ただしこの他にも、「どのように食べたか」に問題があることもまた牛たちの体調不良とは切っても切れない関係であり、厄介な問題のひとつです。
分娩直前に食欲が落ちて必要な量をしっかり食べられず→ルーメン環境の整わない痩せた身体のまま分娩を迎え→分娩後にも食欲は戻らない、なんていう牛たちは、乳熱の治りが悪かったり…分娩直後からケトーシスに陥ってぐったりしてしまったり…挙げ句の果てに四変、なんてことも現場ではよく聞く話です。そんな牛たちを見ていて、自分で自分のごはんを用意しなくてはならない一人暮らし歴10年目に突入した人間としては、「栄養バランスよく・過不足なく・毎日食べ続ける」ことの、自分の身体にとっての大切さを痛いほど感じさせられるのです。
乾草より、味の濃いTMRや配合ばかり食べたい日があるかもしれない。食欲がなんとなく湧かない日もあるかもしれない。そんな日がたまに1日ぐらいあっても大したことはないですが、週単位、月単位で続いてしまったら?
栄養バランスよくエサを食べなかった牛のルーメン環境は乱れ、万病のもととなります。食べ過ぎた牛には無駄な脂肪がついてⅡ型ケトーシスに直結しますし、十分に食べなかった牛は痩せて免疫力が落ち、生殖・泌乳サイクルを回すエネルギーはすり減っていきます。

「食べたもの」はやがて身体の一部となり、「どのように食べたか」はやがて健康状態に直結すること。すなわち、「食べること」はすべての生き物にとって「生きること」そのものであること。
牛たちの生活を見ていれば当然のようにわかった気がしていましたが、では自分の食生活はどうでしょう?バランスを考えず、食べたいものばかり選んでいないか?今日は疲れたからと夜にたくさん食べてしまう日が何日も続いていないか?私も牛たちのように、誰かに決められた食事だけを与えられていれば、どんなに健康的な生活だったか…と考えることも少なくありません。

今回はここまでになります。後編はコチラ
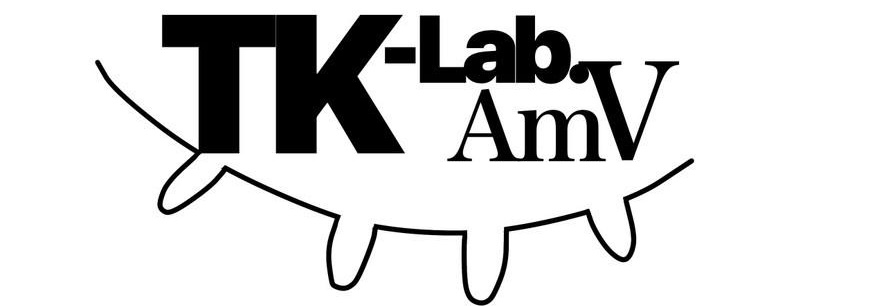



コメント